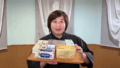栗のお菓子を、自家製の「栗の渋皮煮」で作ってみませんか?
モンブランや栗のケーキ、タルト、ロールケーキなどに使えば、
栗本来の風味がぐっと際立ち、ひと口で贅沢な気持ちになります。
秋になると、ご近所さんや友人から栗をいただく機会も増えてきますね。
「今年こそ、栗の渋皮煮にチャレンジしたい!」
でも、時間も手間もかかるし、失敗したくない…そんな方に向けて。
この記事では、栗の選び方から下処理、ビンの消毒、洋酒の選び方、
そして長期保存できる脱気の方法まで、コツをまとめました。
動画で見る 極上!栗の渋皮煮の作り方
Youtubeに公開しました。
所要時間:約18分
極上!栗の渋皮煮|作り方

【材料】(500mlビン2本分)
栗 500g
重曹 小さじ1〜
砂糖(粗製糖) 鬼皮をむいた重さの70%
バニラ棒 1/2本
(洋酒はお好みで:大さじ1/2〜)
栗の分量について
はじめてのチャレンジは、栗500gが作りやすい。
家庭用コンロの火力・鍋の大きさだと500g〜2kgがおすすめ。
鍋のサイズに合わせて量を決めます。
栗の渋皮煮におすすめの品種
銀寄(ぎんよせ)が断然おすすめです。
いろいろな品種で試してみて気づいたのは、
栗の種類によって「アク抜きのしやすさ」や
「割れにくさ」がまったく違うということ。
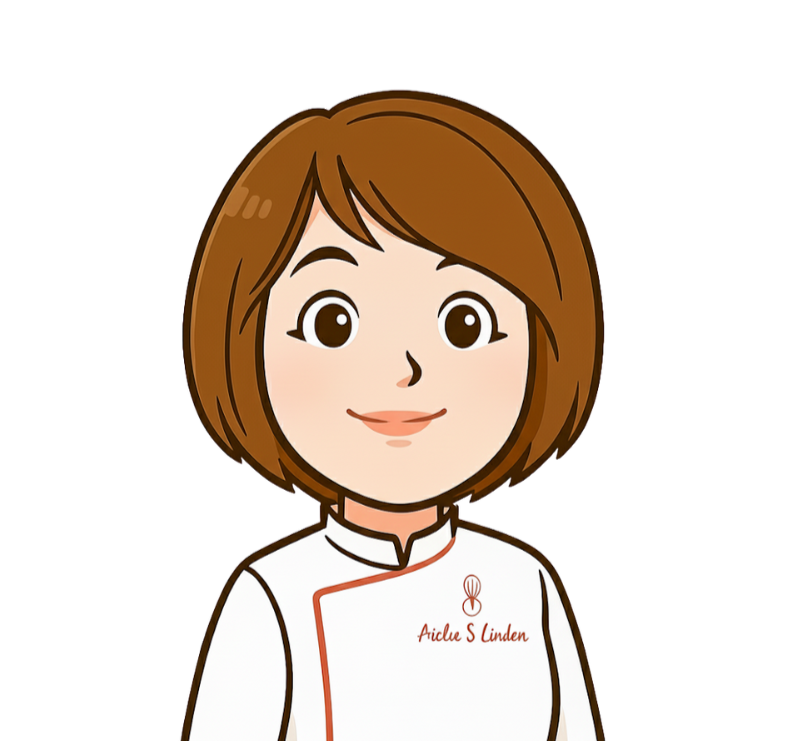
向かない品種に当たると、
丁寧に作っても途中で割れたり、
作業がとても大変になってしまいます。
その点、銀寄は皮がむきやすく、アク抜き作業もスムーズ。
9月中旬〜10月上旬に出回る大粒の品種で、
和栗らしい香りと、なめらかな舌ざわりが特徴です。
私はお菓子販売や対面レッスンなど、
「ここぞ」というときは銀寄を選びます。
品種がわからないことが多いし、他の品種でも良いですが
確実においしくしたい時は、取り寄せてみてください。
ひと味違う、ワンランク上の渋皮煮に仕上がります。
栗の渋皮煮の作り方
鬼皮をむく

栗を洗って、50℃程に沸かした湯に10分ほどつけておく。
温度が下がったら火にかけてキープします。
鬼皮がむきやすくなります。
浮くものは実が縮んでいることがありますので
取り除いています。

水をはったボウル、ペティナイフを用意します。
テーブルにシートを敷いておくと、後片付けが楽です。

鬼皮をむく。
座(ザラザラした方)を上にもって、境目の部分より
少しだけ上からナイフを入れて、下に向かってはがし取る。

深くナイフを入れすぎると、渋皮に傷がつきます。
大きな傷がついたものは、使えないので、よけておく。

栗が乾燥しないように、すぐに水につけます。
アク抜きと渋皮のそうじ
栗の状態によって回数は変わります。
だいたい3回。
アクが強いと4~5回かかることもあります。
1回目

鍋に栗とたっぷりの水を入れて火にかけ、
重曹(タンサン)小さじ1~を加える。
沸いたら、弱火にして10分煮る。

アクが多い1回目は短かく、2回・3回は長めにします。

鍋ごと流しに移動して、蛇口の湯を注ぐ。
栗に直接水が当たらないよう、鍋のフチから流すのがコツ。

水が入れ替わって透明になればOK
急激に温度が下がると割れる原因になるため
湯を注いで、温度を下げながら水を入れ替えます。

流水の下で、指の腹で渋皮をこすり取る。
ガーゼを指に巻いてこすってもOK。
スジは、楊枝で丁寧に取り除く。
1回目はあらかた渋皮がとれたらよい。
くっついているものが無理にはがし取らなくてよい。
2回目

同様に重曹小さじ1を加えて15分煮る。

アクが気になれば取り除く。

透明になるまで湯を注ぐ。

残っている渋皮を丁寧に取り除く。
楊枝の側面でこするようにして渋皮を取り除く。

3回目
重曹は入れずに、同様に15分煮る。

透明になるまで湯を注ぐ。
重曹を抜くため、1時間ほど水につけておく。

休憩できるタイミング
ここでひと晩水につけたままにして
続きは翌日に作業してもよい。
私は1日目にここまで作業し、休むことが多いです。
割れた栗を取り除く

多少の傷は問題ありません。

このように大きく割れたものは粉々になって
シロップが濁るので取り除きます。
砂糖を計量する

栗の重さの70%の砂糖を計量する。
砂糖の量は60〜100%で好みの甘さに調整してください。
砂糖を加える
砂糖の種類について

砂糖の種類は好みでOK。私は「粗製糖」を使用しました。

てんさい糖がお好みの方はこちらもあります。
もちろん、きび砂糖や、グラニュー糖でも大丈夫です。
砂糖を3回に分けて加える
【1回目】

鍋に栗とかぶるくらいの水を入れる。

砂糖の1/3量を加えて、
オーブンペーパーで落とし蓋をして10分弱火で煮る。
火を止めて半日おく。
動画ではひと晩おきましたが6時間くらいでもOK
休憩できるタイミング
1回目の砂糖を加えて1日おいてから
翌日、続きの作業をしてもOK。
【2回目】

砂糖の1/3量を加えて10分煮る。半日おく。

砂糖の1/3量を加えて10分煮る。半日おく。
【3回目】
砂糖の1/3量を加えて10分煮る。半日おく。

3回に分けて砂糖を浸透させるのが理想ですが、
急ぐときは2回にしたり、時間を早めたりと、
臨機応変に調整しています。
糖度を確かめる

糖度計で糖度をはかってみたところ、49.6でした。
ほぼ50ですね。これは「ブリックス(Brix)」という単位で、
液体に含まれる糖分の割合を示しています。
販売用などで品質を一定に保ちたい場合は、
糖度を調整するために計測します。
洋酒を加えるタイミング
洋酒を加える場合は、最後加えてひと煮立ちさせます。

ラム酒、ブランデー、コニャック、グランマルニエなどが合います。
小さなビンに保存すると、ビンごとに洋酒を変えたり
入れない選択もできます。
ビンに詰める

清潔なビンに入れる。シロップは茶こしでこして入れる。
シロップに栗が完全に浸かるようにしてくださいね。
シロップをこさないと濁りの原因になります。
保存の目安
冷蔵庫で2週間が目安。
冷凍すると1ヶ月。
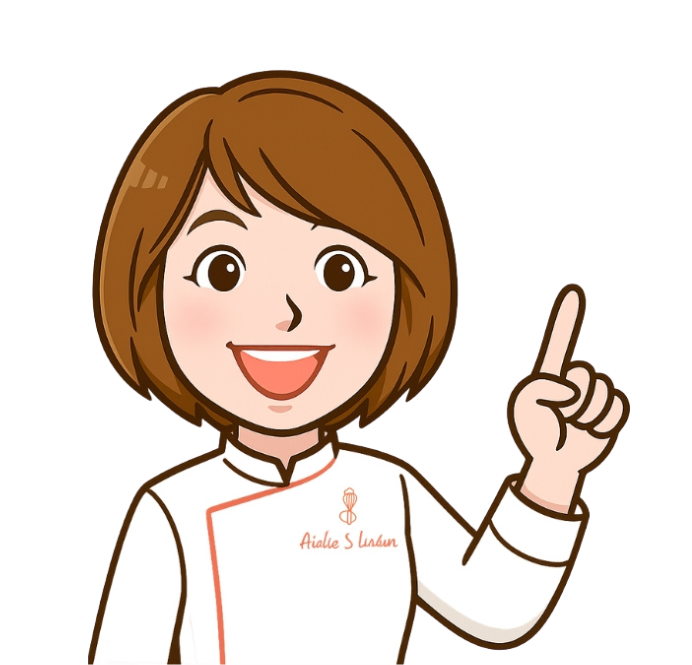
作ってから2~3日おいた方が味が馴染みます。
ビンを煮沸消毒する方法
すぐに食べるなら、アルコールスプレーだけでも良いと思います。
でも、1週間以上保存したい場合や
人に差し上げるときは、消毒した方が安心です。

ビンを洗ってかぶるくらいの水を入れる。
火にかけて沸騰させる。

煮沸消毒の時間
新品のビン:2〜3分
再利用のビン:10分
フタ:30秒(シリコンが劣化するため)
トングや、レードルなど使用しる器具も忘れずに。
煮沸消毒できない器具は、アルコールスプレーをかけます。

ビンを取り出して口を下に向けておく。
清潔なふきんや、アミの上にのせるとよい。
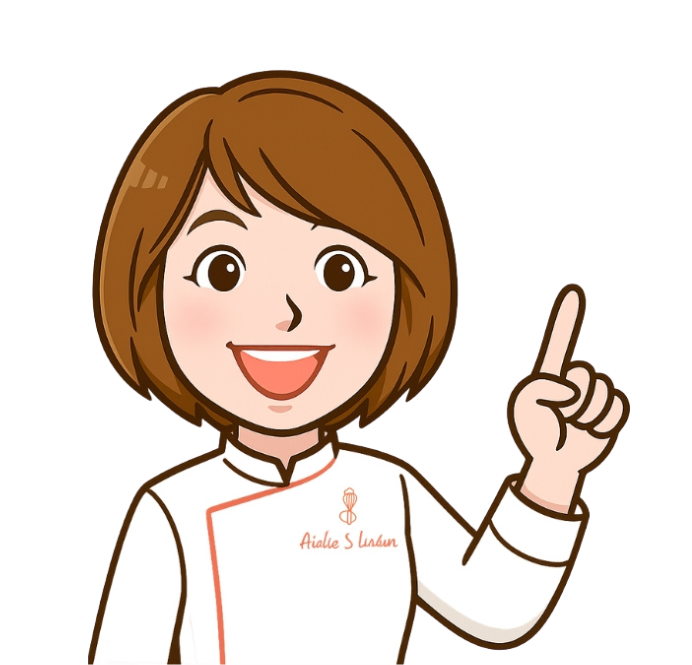
ビンはセリア(100円均一)で購入しました。
脱気して長期保存する方法
長期保存したいときは脱気処理をしましょう。
正しく脱気できていると、冷暗所で1年間は保存できます。
① シロップは8~9分目を目安に入れます。
フタを軽くしめて、少しだけゆるめます。
上に空間がないと脱気できませんのでご注意下さい。

② 鍋底にキッチンペーパーを敷き、ビンの肩まで湯につかった状態にする。
ビンを煮沸消毒した鍋をそのまま使います。
画像は寸胴、深鍋が必要です。

フタをして沸騰してから15分加熱する。(約500mlビンの場合)
時間はビンの大きさによって変わります。

ビンがカタカタ音がしたり、フタがゆるんでくるようなら
菜箸などで空間を開けるとおさまります。
③ 取り出して、フタを開ける方向にねじって
空気を逃がし(脱気)素早くフタをしめる。
脱気できていたら、プスッという小さな音がします。

④ 再び鍋に戻してフタをして10分加熱する。
⑤ ビンをとりだして段階的に冷ます。
60℃くらいの湯に5分ほどつけておく。

取り出して立てたまま冷ます。

急激に冷めるとビンが温度差で割れる原因になりますので
ゆるやかに温度を下げています。
冷暗所で保存くださいね!
1年間、栗のお菓子が楽しめますよ。
脱気に対応したビンとフタを用意します。
フタの使い回しはおすすめしません。
必ず、新しいフタを用意ください。
LINEでレシピPDFを受け取れる

期間限定で、栗の渋皮煮レシピをプレゼントしています。
公式LINEに登録のうえ、キーワードを送ってくださいね。
自動返信でレシピが届きます。
ちなみに、よくある間違いが「栗の渋川煮」
正しくは「栗の渋皮煮」です。
動画は最初こそ、動きが見られて分かりやすいのですが
何度か作っていると手元にレシピがあった方が
サッと確認できて便利ですよ♪
栗のお菓子
モンブランのツリーケーキ
クリスマスに対面レッスンしたものです。
動画レッスンもあります。

栗のケーキ
販売されている方もいる人気メニュー。

自家製栗の渋皮煮で、いろいろ楽しんでみてくさい。